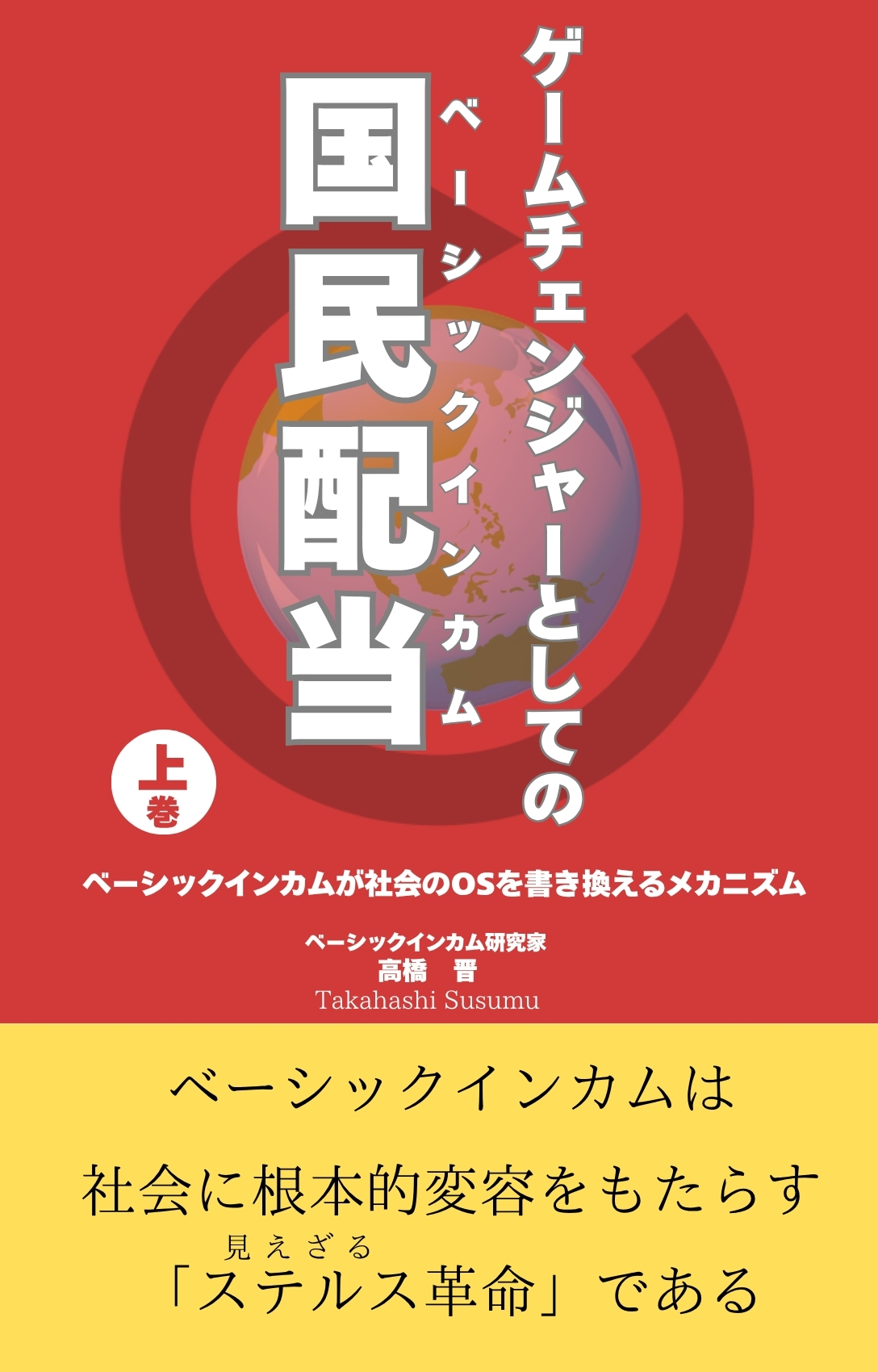「お金の制度」ではなく、「生き方のデザイン」——ベーシックインカムの本当の話
ベーシックインカム(以下、BI)と聞くと、多くの人は「毎月、お金がもらえる制度のことだろう?」と思うかもしれない。
たしかにBIは、すべての市民に無条件で一定額のお金を配る制度である。しかし、これを単なる「給付制度」ーーつまりお金の話ーーと捉えると、その本質を見誤ってしまう。
なぜならBIは、単なる貧困対策や景気刺激策としての現金給付制度ではなく、「社会のあり方」と「私たちの生き方」そのものを根本から問い直す哲学的な提案としての性格も持っているからである。
想像してみてほしい。「とりあえず、来月も生きられる」という最低限の安心が、すべての人に保障されている社会を。そのとき、あなたの行動や人間関係は、どう変わるだろうか?
現在、私たちの多くは「生活のために働く」ことを大前提に人生を設計している。たとえば、どんな仕事を選ぶか、どんな人と関わるか、どこに住むか——その多くが「生きていくために必要な収入をどう確保するか」というその大前提に縛られているのが現実だ。
だが、もし大前提として“生きるための最低条件”があらかじめ保障されている社会だとしたらどうだろう? 人は「生活のために働くにはどうするか?」より、「どう生きたいか?」「何がしたいか?」を基準にその生き方を選ぶようになるのではないだろうか? 働くことが「義務」ではなく単なる「選択」のひとつになる社会——それがBIのもたらす本質的な変化である。
BIは“お金の配り方”ではなく、“生き方の再設計”
BIを「お金の話」だと思うと、「そんな財源はあるのか」「働く人が減るのでは」など、経済的な議論に終始してしまう。もちろんそれも大事だが、BIの本質はもっと根っこの部分にある。
それは、「人間をどのように位置づける社会をつくるか」という根源的な問いだ。人を「労働力」として扱う社会から、「存在そのものに価値がある」と認める社会へーー。BIには、その大胆な転換を静かに、しかし確実に促す力がある。
言い換えれば、BIが提示しているのは経済政策ではなく、人間観のアップデートなのである。「稼ぐ人が偉い」「働けない人は劣っている」という金銭&労働至上主義的な社会から、「誰もが、ただ生きているだけで社会の一員として尊重される」という当たり前の価値が再び中心に据えられる社会へ。それがBIが切り開こうとする新しい社会の姿である。
こう考えてみると、BIというのは、たんにお金の分配をめぐる経済的な議論の対象でないのがわかるだろう。それは、社会そのもののあり方を根本から問い直す社会学的、文明論的な試みであり、同時に「人間観」をめぐる哲学的な議論に他ならないのである。
この文章は私の著書『ゲームチェンジャーとしてのベーシックインカム』をベースに新たに書き起こした記事です。この記事の背景にある考え方に興味を持たれた方は、この機会にぜひこちら↓もお読みください。