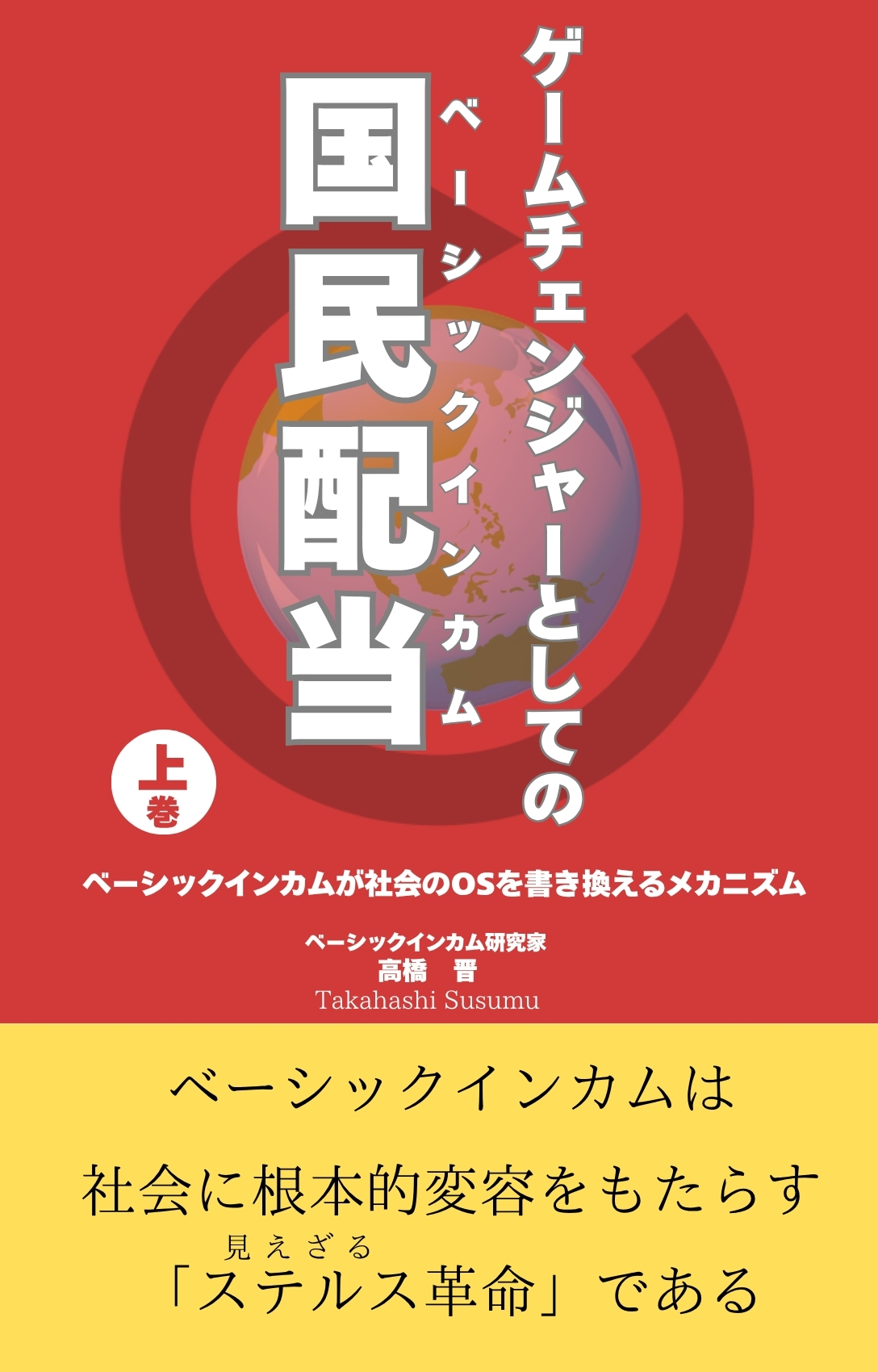働かなくても生きていける社会は、“怠け者の天国”ではない
——「生きるための労働」から、「生かすための仕事」へ。
働かなくなる?という誤解
ベーシックインカム(以下、BI)と聞くと、多くの人がまずこう思う。
「そんなことをしたら、誰も働かなくなるんじゃないか?」と。
たしかに、「働かなくてもお金がもらえる」と聞けば、人は怠けるようになる——そう考えるのは自然な反応かもしれない。
だが、もう少し深く考えてみよう。本当にそうだろうか?
「働かない=悪」という思い込み
近代社会では、「働くこと」は美徳であり、「働かないこと」は恥とされてきた。
この価値観は、産業革命以降の資本主義の歴史と深く結びついている。
生産を拡大し、利益を最大化するためには、人々に長く、安定して労働させる必要があった。
そのため国家は、「働かざる者食うべからず」という倫理を国民の心に植え付けたのである。
つまり、この倫理は、もともと「資本主義を維持するための装置」にすぎないのである。
しかし、長い間、そのことを当然視してきた私たちはもはや「生きるために働く」ことに対して何の疑問も持たなくなっている。
その結果、「働かない=怠け」と思い込むようになったのだ。
では、もし「生きるために働く」という前提そのものが崩れたらどうなるだろうか。
働くことの意味が変わるとき
BIが導入されれば、「働かなくても生きていける」社会が現実になる。
だが、それは「何もしないでだらだら暮らす社会」ではない。
むしろ、「何のために働くのか?」という根源的な問いが、初めて真剣に問われる社会になるだろう。
これまでの社会では、多くの人が「生活のため」「給料のため」に働いてきた。
しかし、BIがあれば、生存のために自分の時間を切り売りする必要がなくなる。
そうなったとき、人々はおそらくこう言うだろう。
「好きだから働く」「誰かの役に立ちたいから」「社会をよくしたいから」と。
つまり、BIによって生まれるのは、「働かない自由」と同時に、
「本当に働きたいことを選択する自由」なのだ。
「怠け者の天国」ではなく、「創造者の楽園」へ
「働かなくても生きていける社会」は、怠け者の天国ではない。
それは、恐怖や義務によってではなく、自由意志と好奇心によって人が動く社会である。
誰もが自分の関心や才能を活かし、他者と協働しながら新しい価値を生み出す。
そうした創造的な活動が、これまで以上に豊かに広がっていくだろう。
芸術、研究、地域活動、子育て、介護——
社会にとって不可欠なのに「お金になりにくい」仕事は数え切れないほどある。
BIは、そうした「見えない仕事」を支える新しい基盤になるのだ。
「生きるための労働」から「生かすための仕事」へ
BIがもたらすのは、「生きるための労働」からの解放である。
その先には、「生かすための仕事」——すなわち、他者や社会、地球全体をよりよくするための活動が待っている。
この転換こそが、資本主義を超えたポスト資本主義社会への道を開くものである。
「働かなくても生きていける社会」とは、怠け者の天国ではなく、人間が本来の創造性を取り戻す社会だ。
そしてそこでは、誰もが“生きる”という仕事に、はじめて集中できるようになるのだ。
この文章は私の著書『ゲームチェンジャーとしてのベーシックインカム』をベースに新たに書き起こした記事です。この記事の背景にある考え方に興味を持たれた方は、この機会にぜひこちら↓もお読みください。