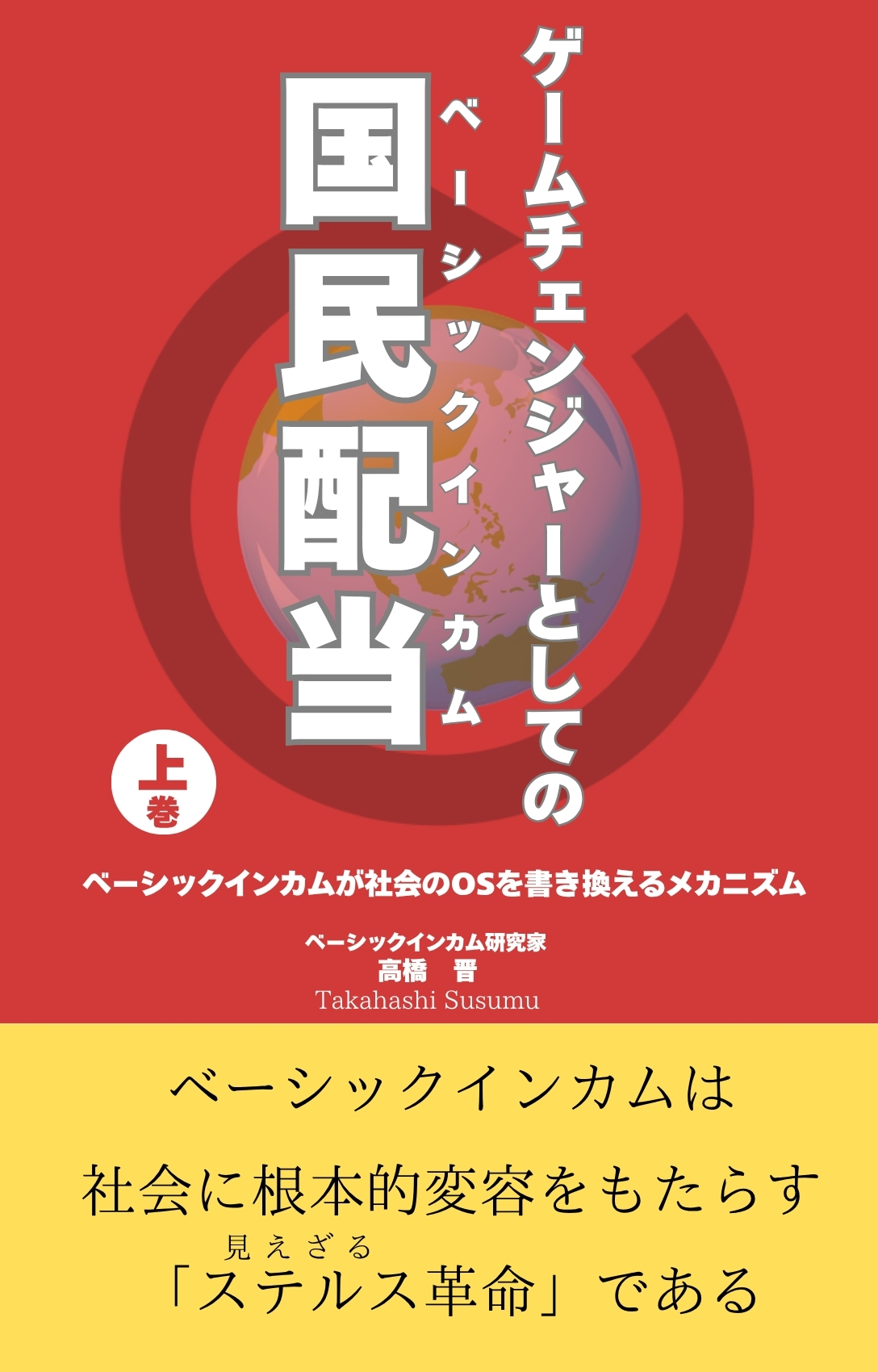ベーシックインカムの基礎知識――すべての人に「生きるための土台」を
ベーシックインカム(以下、BI)という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。
ですが、いざ「それってどんな制度なの?」と聞かれると、意外と説明が難しいものです。
そこで今回は、BIの基本的な仕組みと考え方を、できるだけシンプルに整理してみたいと思います。
ベーシックインカムとは何か?
BIとは、国民全員に対して、一定額の現金を定期的に支給する制度です。
子どもからお年寄りまで、すべての人が、生まれてから亡くなるまで、毎月決まった金額を受け取る――そんな仕組みになります。
イメージとしては、「年金のような給付を、すべての人に、条件なしで行う」と考えるとわかりやすいでしょう。
つまり、働いていようがいまいが、所得が多かろうが少なかろうが、誰もが同じ金額を受け取ることができるのです。
シンプルだが、まだ固まっていない制度
制度そのものは非常にシンプルですが、実際の中身についてはまだ完全には固まっていません。
というのも、「何をBIと呼ぶのか」という定義が、専門家の間でも一致していないからです。
たとえば、
支給額はいくらが妥当なのか?
「定期的」とは毎月のことなのか、四半期ごとなのか、はたまた毎年なのか?
子どもにも大人と同額を支給するのか?
外国人居住者も対象に含むのか?
こうした細部に関しては、論者によって考え方が分かれています。
つまり、BIという言葉にはかなり幅があるのが現状です。
世界的な基準──BIENの定義
しかし、まったく基準がないのも困るーーということで提案されたのが、1986年に設立された国際的ネットワーク「BIEN(ベーシックインカム地球ネットワーク)による定義です。
それによると、ベーシックインカムとは、次のようなものになります。
「資力調査や就労要件がなく、すべての個人に対して無条件に支払われる定期的な現金給付」
つまり、
① 無条件であること(働いているかどうかを問わない)
② 個人単位で支給されること(世帯単位ではない)
③ 定期的に支払われること(継続性がある)
がポイントです。
「UBI」と呼ばれることもある
この「すべての人に配る」という点をより明確にするため、
「ユニバーサル(普遍的)」という言葉をつけて UBI(Universal Basic Income) と呼ぶ場合もあります。
もっとも、BIという言葉自体にはすでに「すべての個人に無条件で支給する」という意味が含まれていますので、UBIは重複表現でもあります。
それでも近年は、「条件付きの給付」までBIと呼ぶ例が増えたため、“本来の無条件型BI”を強調したいときにUBIという呼称を使うケースが多いようです。
他にも様々な呼称がある
ベーシックインカムには、実は他にもさまざまな呼び名があります。
「基礎所得」「市民所得」「国民配当」「社会配当」などがそれにあたります。
これらは、制度の中身が違うというより、それをどう捉えるかという思想的な立場の違いを反映した呼び名です。
たとえば次の通りです。
基礎所得/市民所得
→ 個人の自由や自立を重んじる、リベラルあるいは個人主義的な立場。
国民配当/社会配当
→ 社会全体で生み出された富を国民に還元すべきだという、社会民主主義的な立場。
ちなみに「基礎所得」という訳語は、英語の “Basic Income” をそのまま直訳したものであり、カタカナの「ベーシックインカム」という言い方が一般化する以前、主に研究者の間で用いられていた呼称です。
おわりに
ベーシックインカムは、まだ実験段階にある制度です。
ですが、その発想の根底には、
「人間は誰もが、貨幣の有無に関係なく生きる権利をもつ」
という普遍的な理念があります。
BIは、その理念を現実の制度に落とし込もうとする試みであり、
いわば「生きることの最低限を、社会全体で支える新しい仕組み」です。
この制度を理解することは、
これからの社会がどのような方向に進むべきかを考えるうえで、欠かせない第一歩となるでしょう。
この文章は私の著書『ゲームチェンジャーとしてのベーシックインカム』をベースに新たに書き起こした記事です。この記事の背景にある考え方に興味を持たれた方は、ぜひこちら↓もお読みください。