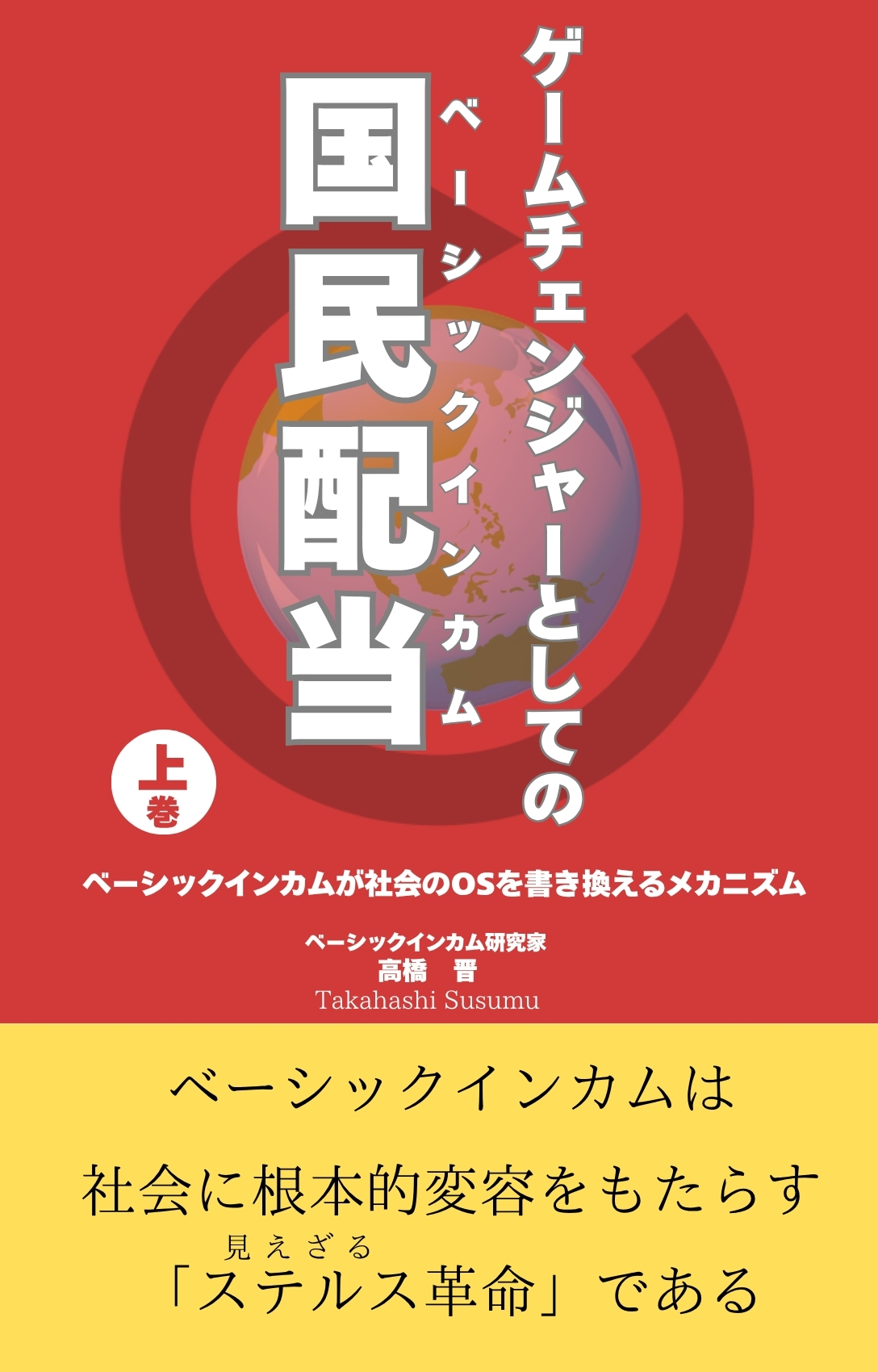ベーシックインカムの原理——「分け合う社会」は幻想ではない
ベーシックインカム(以下、BI)の考え方は、実のところ驚くほどシンプルだ。根底にあるのは「モノが余ったら分け合えばいい」という、ごく単純な原理である。
■ 10人の村のたとえ
たとえば、ここに10人が暮らす小さな村があるとしよう。そして、農業技術の発達によって、いつか1人で10人分の食料を生産できるようになったとしよう。そうなれば、残りの9人は働かなくても食べていけることになる。10人分の食料がある以上、それを平等に分ければよいだけの話だからである。
つまり、生産力の向上によって、10人のうち9人が「働かずに生きていける」社会が成り立つ。この単純な発想こそ、BIの原理の出発点にある考え方だ。
■ 「遊んで暮らす奴らを食わせるのか?」という反発
もちろん、現実はそう単純ではない。もしこのような提案を現代社会で行えば、「遊んで暮らす奴らをなんで俺が食わせなきゃならないんだ?」という声が必ずあがるだろう。
働く人の不満はもっともである。自分が汗水垂らして働いた成果を、何もしていない人と分け合うのは理屈としてはもちろん感情的にも納得しがたい。そして決まってこうした指摘が出てくる。「ほらみろ、そんな単純な理屈では社会は成り立たない。共産主義の二の舞になるだけだ」と。
しかし、本当にそうだろうか。人は本来、常に「自分の生産物を自分だけのものにしたい」と思う存在なのだろうか。他者と分け合うことを、私たちはまったく望まない生き物なのだろうか。
■ 人類の本能は「分け合う」ことにあった
人類学や歴史学の知見は、まったく逆のことを示している。たとえば、狩猟採集社会では、獲物を共同体の中で分け合うのが当然だった。独り占めは恥ずべき行為とされ、しばしば厳しく禁じられていた。
また、自分の家で消費しきれない食料を近所に分けたり、贈り物を交わす風習は、未開社会に限らず現代の先進国にも根強く残っている。これらの事実は、人間の心の奥底に「独占よりも分かち合いを良しとする傾向」があることを示している。
なぜそうなのかという問いはここでは脇に置くとして、少なくとも言えるのは、「分け合う社会」は何万年ものあいだ人類の標準だったということである。むしろ、「独り占めすることが許される社会」は近世以降に登場した、きわめて特殊な歴史的形態にすぎない。その歴史は、わずか数百年程度である。
■ 「分け合う社会」は過去の遺物ではない
「分け合う社会」というと、「原始共産社会」という言葉を思い浮かべる人もいるだろう。そしてそれは、すでに歴史の博物館に収められた過去の遺物にすぎないと考える人も多い。だが、本当にそうだろうか。
もしそのような社会が数万年にもわたって存続してきたのだとすれば、そこには何らかの「持続するだけの理由」があったと考える方が自然ではないだろうか。古いからといって価値がないとは限らない。むしろ、長く続いたものの中には、現代社会が見失った知恵が潜んでいる可能性がある。
■ ベーシックインカムの可能性
実は、ベーシックインカムは、そうした「分け合う社会」を現代的に再構築するための試みでもある。それは理想主義者が思い描く単なる夢物語ではない。人類史において長く続いてきた「分配の知恵」を、テクノロジーと制度設計を通じて現代社会に蘇らせようとする試みなのだ。
BIという発想は、たしかに一見すると単純な思いつきのように見える。けれど、その背景には何世紀にもわたる深い思索と議論の蓄積がある。それは物理学の基本方程式E=mc²が、何世紀にもわたる学者たちの無数の考察と試行錯誤の末に導き出されたことにも似ている。あっけないほど単純なこの方程式は、だからこそ宇宙の真理を端的に表現しているともいえる。
BIも同様である。それは驚くほど単純でシンプルだ。しかし、だからこそ、複雑きわまる社会問題を遍く(というのはちょっと言い過ぎだが)解決に導く万能薬になる可能性を秘めているのである。
この文章は私の著書『ゲームチェンジャーとしてのベーシックインカム』をベースに新たに書き起こした記事です。この記事の背景にある考え方に興味を持たれた方は、ぜひこちら↓もお読みください。