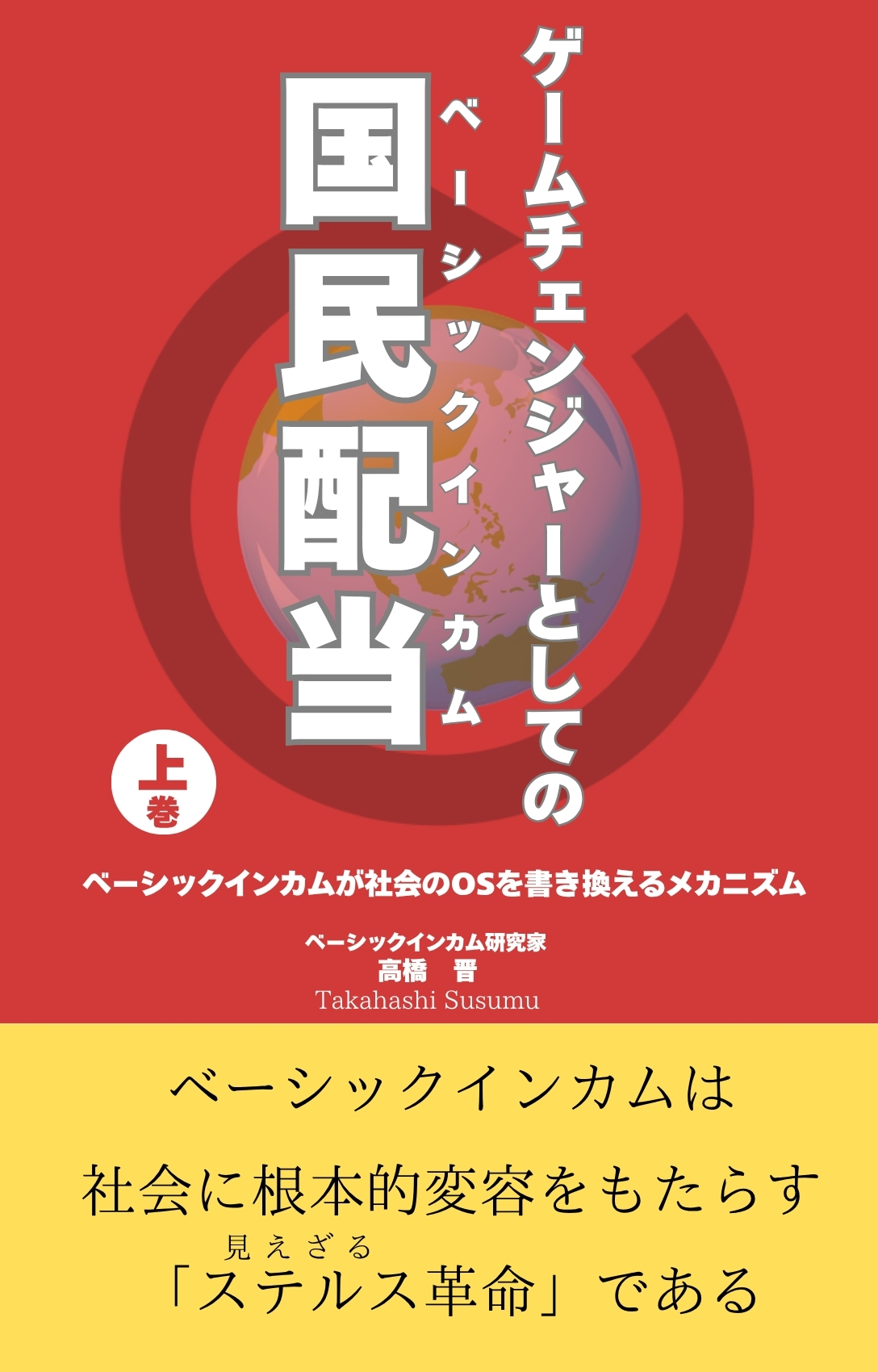社会のOSをアップデートするベーシックインカム
ベーシックインカム(以下、BI)と聞くと、多くの人は「毎月、お金がもらえる制度のことだろう?」と思うかもしれない。
たしかにBIは、すべての市民に無条件で一定額のお金を配る制度である。しかし、これを単なる「給付制度」と捉えると、その本質を見誤ってしまう。
なぜならBIは、貧困対策のための手当ではなく、「社会のあり方」そのものを問い直す提案だからである。
想像してみてほしい。「とりあえず、来月も生きられる」という最低限の安心が、すべての人に保障されている社会を。そのとき、あなたの行動や人間関係は、どう変わるだろうか?
現在、私たちの多くは「生活のために働く」ことを大前提に人生を設計している。どんな仕事を選ぶか、またどんな人と関わるかも、その前提に縛られている。
だが、もし大前提として“生きるための最低条件”があらかじめ保障されている社会だとしたらどうだろう? 人は「生活のために働くにはどうするか?」より、「どう生きたいか?」「何がしたいか?」を基準にその生き方を選べるようになるはずだ。
BIとは、単なる「分配」ではなく、「社会の前提条件そのものを書き換える」試みである。社会をゲームにたとえるなら、それはルールブックの第一章を書き換える行為に等しい。すなわち「生存競争を目的とするゲーム」から、「自己実現を目的とするゲーム」への転換である。
「社会のOS」をアップデートするということ
パソコンやスマホで、OS(オペレーティングシステム)が古いままだと不具合が起きる。どんなにアプリ(個々の制度や政策)を改善しても、根本の仕組みが古ければ動かない。いまの社会もそれと同じである。
現代の「社会OS」は、19世紀の産業資本主義を前提に設計されている。その根底にあるのは、人が働くことで所得を得て、そこでの消費が経済を回すという仕組みだ。しかし、AIおよびロボットによる自動化が進み、人手のいらない生産が増えていくなかで、その前提はすでに現実とズレ始めている。
BIは、単なる「アプリの追加」ではなく、この社会OSそのもののアップデートを意味する。「働く人だけが生きられる社会」から、「すべての人が生きる権利をもつ社会」へ。その書き換えを静かに実現する仕組みが、BIなのだ。
BIを福祉政策だと誤解する人が多いのは、「お金を恵んでもらう」という上下関係のイメージがつきまとうからだろう。しかしBIは、誰かの恵みでも上からの施しでもない。それは「共同体の成員として誰もがもつ生得の権利」を分配するものであり、それを制度として可視化するものだ。
社会は、すべての人が関わり合うことで成り立っている。家族や地域共同体といった基礎的な社会基盤、そこから生まれる文化やモラル、また道路や水道、金融システムなどの公共インフラ、そして今の私たちが享受する豊かな暮らしを実現する上で決定的な役割を果たした数多の知識や技術という先人たちの遺産……私たちはすでに誰のものでもない多くの“社会的共有資源”の成果の上で生きている。BIは、その共有資源がもたらす果実を、あらためてその本来の所有者であり管理者である市民に公平に分配しようというものである。
つまり、BIは国家が「上からお金を恵む」のではなく、市民が「自らが築いた社会の成果を、自分らに還元する」制度なのである。
BIは“お金の配り方”ではなく、“生き方の再設計”
BIを「お金の話」だと思うと、「そんな財源はあるのか」「働く人が減るのでは」など、経済的な議論に終始してしまう。もちろんそれも大事だが、BIの本質はもっと根っこの部分にある。
それは、「人間をどのように位置づける社会をつくるか」という問いだ。人を「労働力」として扱う社会から、「存在そのものに価値がある」と認める社会へ。
ベーシックインカムとは、単なる給付政策ではなく、社会そのものの哲学を問い直す試みである。それは、お金の話ではなく、「人間観」をめぐる議論に他ならないのである。
この文章は私の著書『ゲームチェンジャーとしてのベーシックインカム』をベースに新たに書き起こした記事です。この記事の背景にある考え方に興味を持たれた方は、この機会にぜひこちら↓もお読みください。